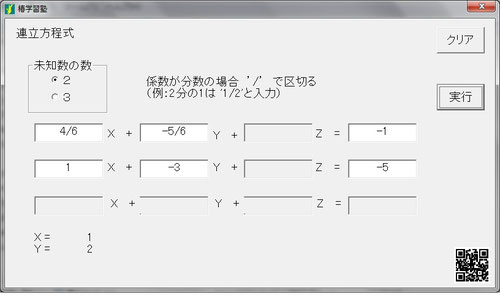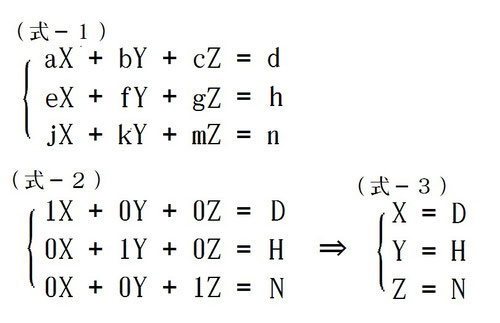連立方程式
連立方程式は、問題を式にするまでが最も重要ですが、今回はコンピュータで方程式式を解くための最も効率のいい方法を説明します。
連立方程式を解くコンピュータソフト
使い方
- 連立方程式のソフトを立ち上げる。
- 未知数が2か3か選択する。
- 入力枠に係数を入力し、実行ボタンを押す。
- 解が表示される。
コンピュータでの連立方程式の解き方
中学生に分るように説明します。
(式-1)の連立方程式の係数を(式-2)のように変形する。
- 左辺の左上から右下への対角の係数をすべて1にする。
- それ以外の左辺の係数をすべて0にする。
- そうすれば右辺に解が現れる。
係数の変形は加減法を応用して(式-2)の形になるまで繰り返す。
(式-2)の係数0の項を省略すると(式-3)の式になり解が求まったことになります。
(この左辺の係数並びを行列の言葉で単位行列と言います)
このソフトは未知数が2と3の場合にしか対応していませんが、
未知数の数が増えても上記の単純処理を繰りかえすだけなので、未知数の数がいくら多くても解くことができます。
解について
3種類の解が考えられます。直線のグラフで考えると分かりやすい。
1.解が1組
直線が1点で交わる場合
2.不定(解が無数にある)
直線が重なる場合
定数倍すると同じ式になる
3.不能(解なし)
直線が並行で交わらない場合
左辺が同じ係数であるにもかかわらず、右辺の係数が異なる。
中学では、1.のタイプの問題しか出ませんが、一般的に3種類の解について考慮する必要があります。

 椿 学 習 塾
椿 学 習 塾